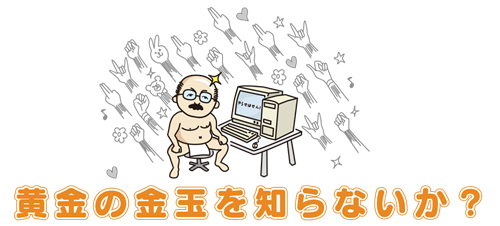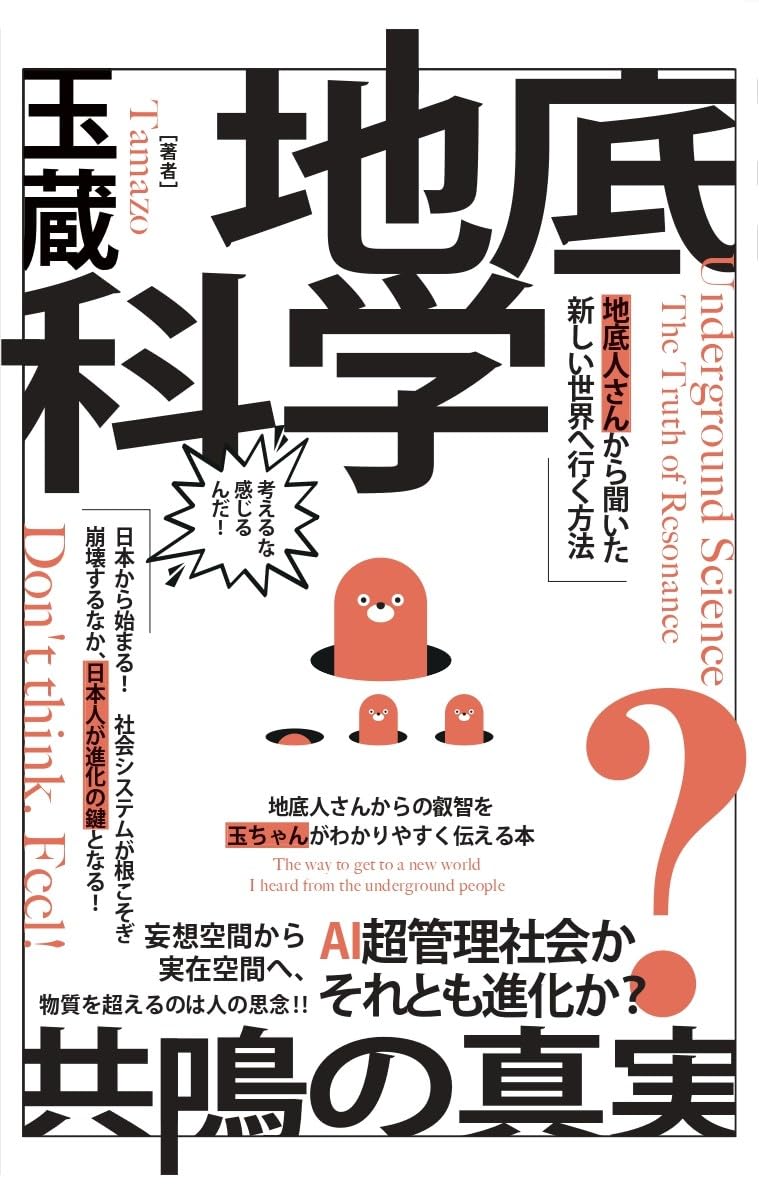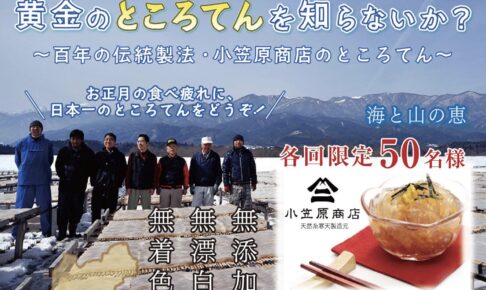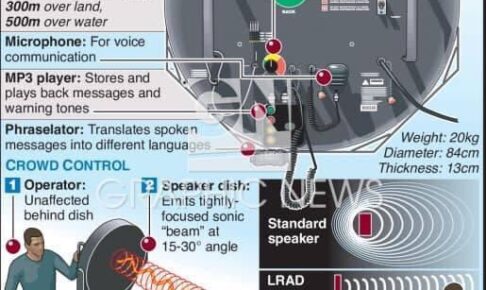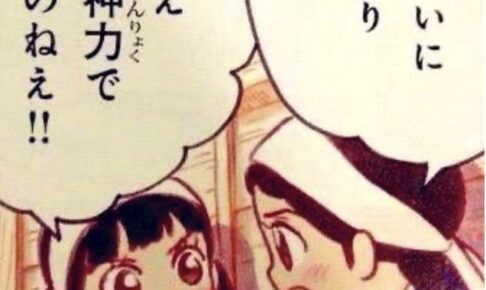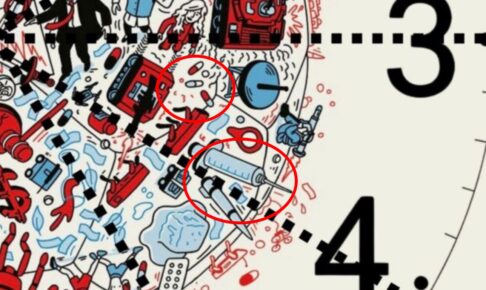さて、世界中にトランプショックが走る中。
我々はそんなことに目もくれず山梨の山奥で黙々と作業していました。
今年になって始まったダーチャプロジェクト。
今回は壁塗りでした。
いや、それにしてもひじょーに楽しいイベントでした。
土と戯れ自然に帰る。
もう今後海の向うの国がどうなろうがどうでも良くなるというものです。
以下、当日の動画です。
楽しさが伝わるかと思います。
こちらは写真。

こども達も喜んでやってました。

なぜか大人もはしゃいでいました。

なぜ土壁にこだわるのか。
土壁の何がそんなに良いのか。今回も高田先生より詳しく説明がありました。












最終的にはこんな綺麗な土壁に仕上がりましたよ。

さて、我々はなぜこんな面倒くさい土壁作りなどやったんでしょうか。
普通に現代風の作りにすれば良いのに。
いいえ。
現代の家の寿命は30年と言われてます。
一方、日本の古来の伝統工法の家の寿命は10倍の300年なのでした。
なぜかテクノロジーの発展したはずの現代の家の方が寿命が短くなってしまう。
それは日本の家が湿度との戦いだからです。
日本のように温暖で雨が多くて湿度の高い土地では当たり前のように木が腐りやすいのです。
例えば輸入物のログハウス。
ログハウスは木を横にして積み上げますが、本当は日本古来のやり方だと木は縦にして使います。
縦にすることで木の中の水分が移動しやすく乾きやすいのです。
現代建築は訳も分からず風土に合ってないやり方を無理やり当てはめるから寿命が縮むのです。
例えば現代建築は柱にコンパネやボードを打ちつけて中は空洞になっている場合が多い。
で、日本の場合は湿度が高いので、その空洞部分に結露が溜まってしまう。
それでカビが生えたりシロアリが発生したりして木の寿命を短くなってしまっているとのことでした。
一方、日本古来の土壁は、竹を格子状に組んだもの上に土と藁を混ぜ醗酵させたものを塗っていきます。
土と砂、藁を混ぜたものを何層にも渡って塗るので中に空洞が出来ない。
だからまったく結露が起こらないのです。
で土壁は、湿気が多くなり過ぎると水分を吸収し、乾燥してくると水分を放出する。
まさに呼吸する壁になっているのでした。
そして寒い冬は土壁は温まりにくい。
しかし、一度温まると今度はさめにくいので長い間その温かさを保つ。
冬の朝、なぜか古民家の壁は暖かさを感じるのはそのためなのでした。
という訳で、日本の風土にあった日本古来の伝統工法。
我々は見た目だけきらびやかで中身がすっからかんな現代建築など使わない。
日本の四季を活かした古来からの伝統技術。
庶民の知恵をそのまま受け継ぐ。
昔懐かし土壁を思い出せ!
今回もひじょーに勉強になりますた。
楽し嬉しのワークショップの報告でした。
本当にありがとうございますた。
イベント情報: ・祝!DENBA代理店になりました ショップ情報: ・農薬不使用!皮ごと食べられる長芋 新芋 5kg 6,000円〜
・オイル交換が不要になる!不思議商品OE9

10/24新刊発売中! ・Kindle版 地底科学 共鳴の真実 AI超管理社会か?それとも進化か?
能登半島地震: ・地球守活動募金先
メルマガ始めました: ・サポーター会員募集中(月額777円)
LINE版 黄金村 隊員連絡網始めました(笑)

関西黄金村 隊員連絡網はこちら